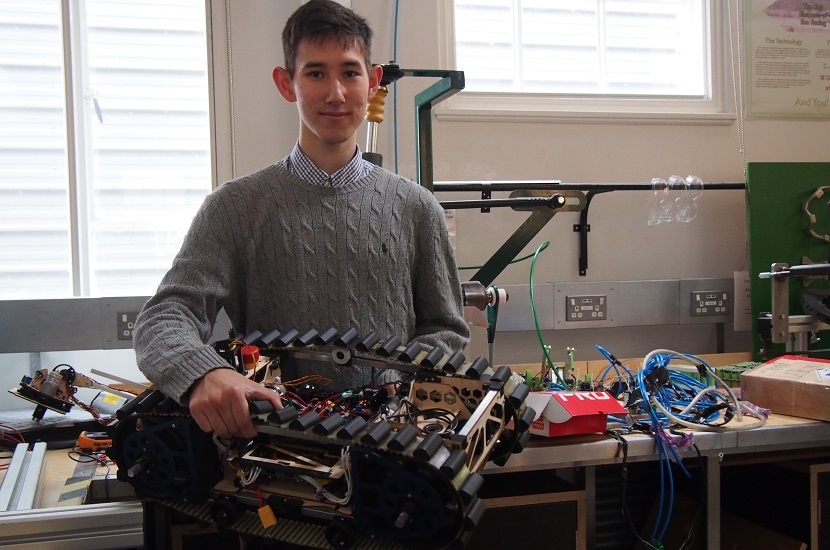 STEAM教育
STEAM教育 ロボット国際大会の経験がケンブリッジ大での学びに通じている~WRO国際大会銀メダリストに聞く未来 前編~
レゴ? マインドストーム?とともに成長してきた人々のストーリーを紹介する本記事では、英国ケンブリッジ大学工学部に通うユング開さんにお話を伺いました。小学生で出会ったロボットプログラミングの世界、国際大会での表彰、英国留学までの道のりをお伝えします。
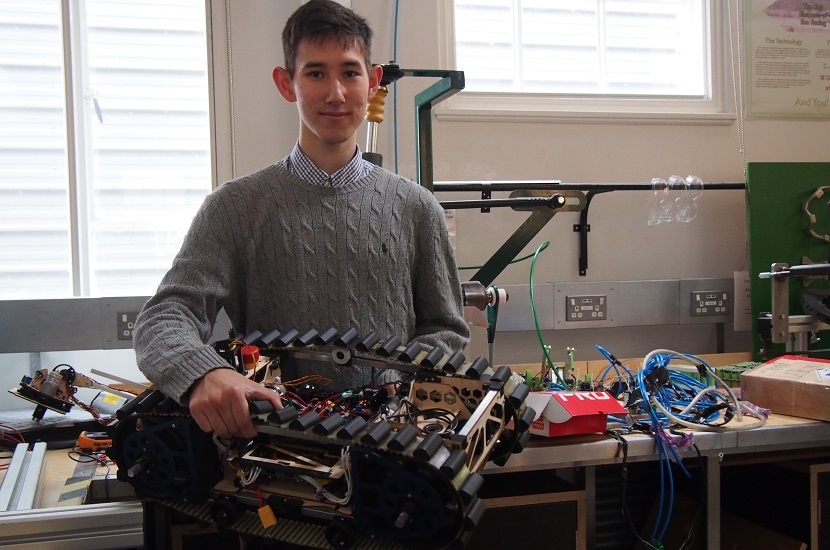 STEAM教育
STEAM教育 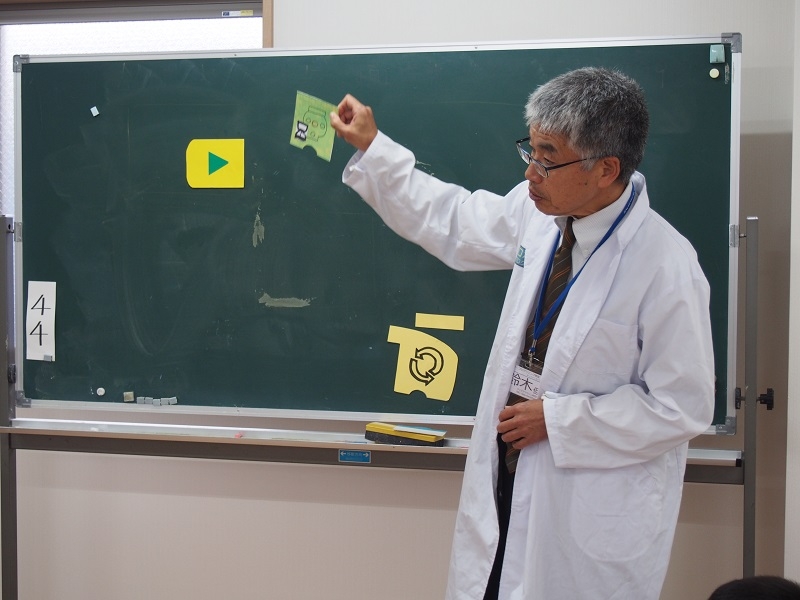 プログラミング教育
プログラミング教育  コンテスト
コンテスト 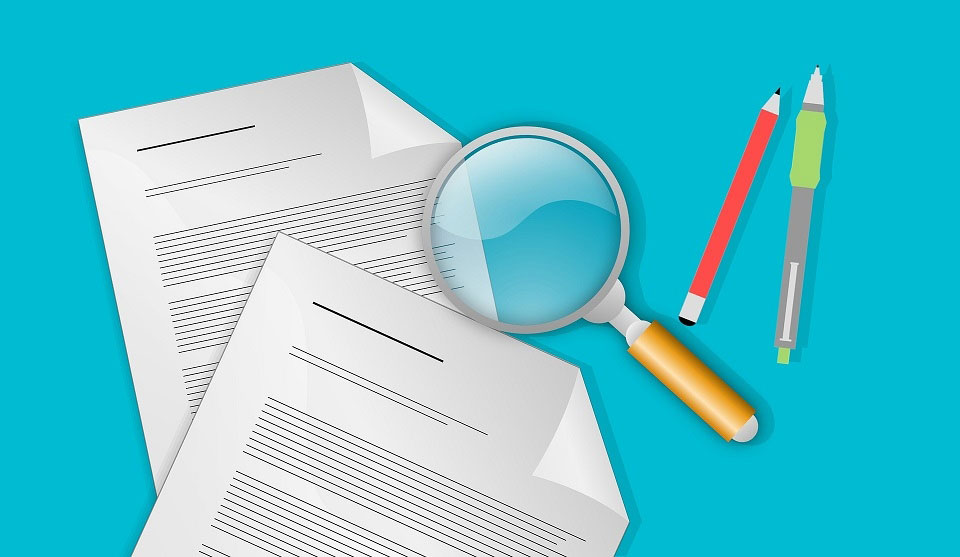 技術情報
技術情報 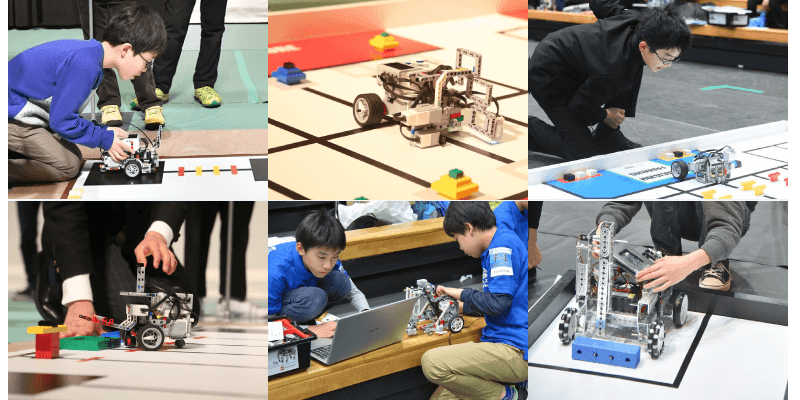 コンテスト
コンテスト  AI
AI  STEAM教育
STEAM教育  ロボット活用事例
ロボット活用事例