函館工業高等専門学校(以下、函館高専)では、産業現場に即した教育を目指し、FA(Factory Automation)およびSIer(System Integrator)を意識したロボット実験を導入しています。
高専教育ならではの実践的アプローチで、新しい学びを形にしています。
知識がつながる学びへ――
FA SIer実験導入の背景と狙い
函館高専では、これまで4年生に「ロボットアームの制御」、5年生に「シーケンス制御」の実験科目を設定しており、学生にとってテーマが異なることで、学びの関連性を見いだせず、知識が繋がらないという課題がありました。令和5年度より、授業カリキュラム見直し伴い実験テーマをこれまでの10テーマから8テーマへ再編。同校は高専「COMPASS5.0のRX/DXの協力校」であるため、産業現場に近づくよう「ロボッSIer」を実験テーマとし、ロボットを”使える人材”の育成を強化することにしました。
<実験の構成と内容>
実験は2名1班、6週間にわたり、90分×2コマを週ごとに実施。
実際の生産現場に近いシナリオを想定し、ロボットとセンサー、コンベヤ、PLC制御といった要素を組み合わせた一連の作業を学生が体験します。
「FA SIer実験」の授業構成は以下の通り
- ロボットの順運動学・逆運動学の復習
- Pythonによる逆運動学制御プログラムの作成
- ロボットアームピック&プレイス
- 画像処理によるピック&プレイス
- PLCを用いたコンベヤ機材のシーケンス制御
- コンベヤとロボットアーム(DOBOT Magician)の統合
最終課題
①DOBOT Magicianを待機位置にて待機させる。その間、他班が制御するDOBOT Magicianが、静止している自班のコンベヤ上端にワークを設置
②さらに1秒静止後、LEDを点滅させながら、コンベヤが順方向に稼働しワークを搬送する
③正常にワークが下端まで搬送されたら、コンベヤおよびLED点滅を停止
④DOBOT Magicianによりワークを搬送
⑤コンベヤはワーク搬出後に初期状態に戻る。DOBOT Magicianは把持したワークを他班のコンベヤ上端に設置後、待機位置に戻る
実験の合格判断基準は「ワークが10周動くこと」とし、ティーチング設定をし、置く場所にズレが起こらないよう丁寧に位置決めをすることを重要としています。
限られた環境で最大の効果を――
教材選定と実験機材の工夫教材選定にあたって
実験テーマを変更し、教材選定をするうえでは以下を考慮して決定しました。
- 2人に1セットの実験環境を用意できる安価で信頼性のある教材
- 学校にて保守できることが重要
- 現有資産を活用しつつ、必要な機能を補完できる構成
活用している機材は以下の通り:
- DOBOT Magician(ロボットアーム)
- OMRON製 コンベヤ&PLC(CP1Lシリーズ)
- 各種センサー(近接・光電センサー/透過型・反射型など)
- 自作ゲート回路基板(24V→3.3V変換)
学生の気づきが未来をつくる
――実験で育まれた実感と実験後の成果
6週にわたる実験を通して、「今までやった実験のなかで一番達成感・満足感がある」と学生たちは言います。卒業後、工場のFAラインの設計に携わることが多いため、FAシステムを想定した実験を経験したことで、SIerの仕事の一端を考えられるようになったのではないかと今回の実験の成果を感じています。また、当初の狙いにあった「ロボットアームの制御」と「シーケンス制御」を1つのテーマにしたことで、FAを意識させやすくなり、学んできたことを繋げて考え、前週実験した結果「センサーやデータの重要性」も理解できるようになりました。
函館高専では、これらの取り組みをさらに発展させ、企業向け研修などにも応用可能な水準に高めていきたいと考えています。また、PLCをネットワークに接続し、サイバーセキュリティ体験やAGVとの連携など、より高度な技術にも対応できる教材開発を視野に入れています。
現場で“使える力”を育てるために、教育現場ができること。
函館高専の取り組みは、他の高専はもちろん、大学や専門学校など技術教育に携わる教育機関機関にとっても参考になることが多く含まれているのではないでしょうか。今後の教材開発や教育実践に広がっていくことを期待しています。
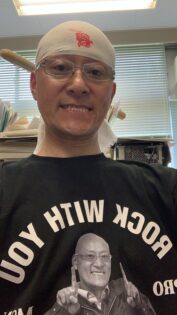 |
函館工業高等専門学校 生産システム工学科 准教授 中村 尚彦 氏 スローライフへの憧れから始めた家庭菜園と愛犬の世話に早朝から追われ、出勤後も7つの部活の顧問・授業・卒研指導に夜まで追われる日々を送っています。ロボット工学は学生時代に装着型歩行支援機の開発を目指して勉強を始めました。現在では、多くの方が定年退職後の生活をより快適に過ごせるよう、生活支援ロボットの必要性を強く感じています。そこで、除雪・除草・家庭菜園の補助・魚釣り支援など、日常のさまざまな場面で活躍できるロボットの開発に取り組んでいます。解決すべき課題も多いのですが、快適な老後生活を目指して日々奮闘しています。 |
